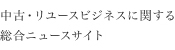和田質店(茨城県水戸市)は1912年(明治45年)、初代・和田末吉が呉服屋「いぎんさん」から独立し、呉服・古着屋を創業したのが発祥です。昭和20年(1945年)頃に蔵を建てて質業に転換。それ以降、時代の変遷に合ったビジネスを展開し、三代目が水戸駅南支店、四代目の時代に日立支店を開店して、茨城県内に3店舗を有する質店に成長しました。
昭和20年頃に蔵を建て質屋を本格的にスタート
初代の実家は和田百貨店
20歳で呉服・古着屋を創業
 左は現在の和田質店外観。建物は建て替えられたが、創業以来同じ場所にある。右は初代・和田末吉氏(左)と二代目・和田誠太郎氏(右)
左は現在の和田質店外観。建物は建て替えられたが、創業以来同じ場所にある。右は初代・和田末吉氏(左)と二代目・和田誠太郎氏(右)
和田質店は明治45年(1912年)、茨城県水戸市に創業した。明治天皇が崩御し、7月30日から大正元年と年号が改められた年だった。創業者で初代の和田末吉は埼玉県羽生市の呉服屋の三男として生まれた。この呉服屋は大正6年に服飾衣料品を販売する和田百貨店となり、現在も営業を続けている。しかし末吉は家業を継ぐ立場になく、10代で水戸の呉服屋「いぎんさん」の丁稚となった。末吉は山っ気のある商売人で、瞬く間に頭角を現して番頭となり、20歳前には独立して和田質店の前身となる呉服屋・古着屋を水戸市の商店街に創業した。
「水戸藩は徳川御三家のひとつで、元々リベラルな藩でした。徳川慶喜の父で9代藩主だった徳川斉昭は特にリベラルな名君で、保守的な人が少ないから、新参者が商売しやすいと思ったのでしょう」と語るのは三代目の和田公一郎氏だ。
水戸の市街地はJR水戸駅の北側が「上市(うわいち)」と呼ばれ、江戸時代は侍が住んだエリアで、南と南東側が「下市(しもいち)」といわれる町人が住んだ下町だった。末吉が店を構えた柳町は下市にあり、1922年(大正11年)から目の前に路面電車が通り、1本裏には芸者町がある繁華街だった。妻のはなは家事を女中に任せて夫と共に商売に精を出し、洗い張りもやっていて、女性のお客が多い店だった。
第606号(2025/04/25発行)18面